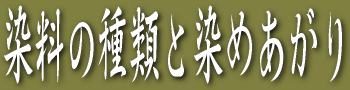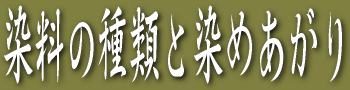|
|
■藍
「出藍の誉れ」(「藍は藍よりい出て藍よりも青し」)の語源として、あまりにも有名な染料です。確かに原料のアイは、タデ科の目立たない草です。染具合によって、出来上がりの色には名前がつけられています。
〔左から〕 1.瓶(かめ)のぞき 2.水浅葱(みずあさぎ)
3.浅葱 4.お納戸(おなんど)
5.紺 6.上紺(じょうこん)
|
 |
■山桃の木の皮
山桃は本邦南西部から東南アジアに分布する常緑高木です。その樹皮を乾燥させたものを染料とします。染めあがった色は白茶から黄色まで。色合いの違いは染料液の濃度にもよりますが、濃い色を出すためには媒染剤に鉄(硫化第一鉄を水に溶かして上澄みを取ったもの)を入れます。黄色味がほしいときにはミョウバンを入れます。 |
 |
■榛(はん)の実
小さな松笠みたいな実をつける榛の木は、日本各地に分布しているので、ご存じの方も多いでしょう。染料にするには、実がまだ緑色のときに取って保存します。色の違いは液の濃度によります。
|
 |
■五倍子(ごばいし。「きぶし」とも呼ぶ)
ヌルデミミアブラムシというアブラムシの仲間が、ヌルデやウルシの木の葉に傷をつけてコブになったものを、乾燥させたものです。タンニンを多く含み、塗料やインクにも利用されます。江戸時代に既婚女性が歯に塗ったオハグロも、これと硫化鉄を混ぜたものだったそうです。 |
 |
■ビンロージュ
インド、マレーシア原産のヤシの一種。東南アジアでは、この実を口中刺激剤として口にする習慣が古くからありました。噛みタバコのようなものらしいです。
漢方薬にも使われますが、黒色の染料としても昔から利用されてきました。 |
 |
■カテキュー
石炭みたいに見えますが、インドや東アフリカに産するアカシア属の植物の心材を煮詰めて作った固形エキスです。これもタンニンを多く含んでいます。 |
 |
■コチニール(カイガラムシ)
カイガラムシはミカンや梨、柿などの果樹や庭木に寄生して木をダメにする害虫ですが、この仲間の一種のラックカイガラムシは、染料になる益虫です。昔から、高級和菓子のピンク色はこれを使ってきたそうですし、化学着色料が評判の悪くなってきた最近では、ほかの食品にも利用されるようになったので、値段が高くなってきています。 |
 |
■化学染料
木綿の赤色は、植物染料では、日にあたると飛んだり、水で洗うと褪せたりして、ちゃんとした色が出ないので、赤だけは化学染料を使っています。ただし、落着いた色にするために、仕上げには植物染料を使います。 |